サステナビリティ経営とは、環境・社会・経済の3つの側面をバランスよく考慮しながら、持続的に成長し続けることを目指す経営の考え方です。
近年、世界のESG投資額(※)は運用資産の4分の1を超え、2030年には40兆ドルを超えると予測されています(Bloomberg Intelligence調べ)。消費者・投資家・規制当局のすべてが企業に持続可能性を求めるようになった今、もはや「やるかやらないか」ではなく「どうやって実践するか」が問われる時代です。
とはいえ現場では、予算の問題、社内浸透の難しさ、成果の可視化、リソース確保といった「4つの壁」に直面するのが実情です。
本記事では、サステナビリティ経営の本質的理解から始め、4つの壁を突破する実践的方法論と、企業の成功事例までを体系的に解説します。
また記事の最後では、実践につながる「企業イベントにおけるサステナビリティの現在地」をご紹介しますので、ぜひご覧ください。
ESG投資額とは・・・環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)の3つの要素を考慮して行われる投資の総額のことです。

サステナビリティ経営とは-定義と本質的理解

「サステナビリティ経営を推進せよ」と言われても、その本質を正確に理解していなければ、方向性を見誤りかねません。ここでは、サステナビリティ経営の明確な定義と、今なぜこれが必須となっているのかを解説します。
定義:環境・社会・経済の統合による価値創造
サステナビリティ経営とは、企業が環境保護、社会的責任、経済的成長の3つを同時に追求し、長期的な企業価値を創造する経営アプローチです。単なる社会貢献活動ではなく、事業戦略の中核に持続可能性を組み込み、社会課題の解決を通じて競争優位性を構築する戦略的経営手法です。
具体的には、カーボンニュートラルへの取り組みによるエネルギーコスト削減、ダイバーシティ推進によるイノベーション創出、サプライチェーンの透明化によるレジリエンス強化など、環境・社会への配慮が直接的に企業の収益性や成長性に寄与する仕組みを構築します。
なぜ今必須なのか-外部圧力と内部要因
ESG投資の急拡大により、世界の運用資産の4分の1がサステナビリティを考慮した投資となっています。さらに、2021年のコーポレートガバナンス・コード改訂により、東証プライム市場上場企業はTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)等のフレームワークに基づく情報開示が実質義務化されました。EUタクソノミーやサプライチェーン全体へのESG規制も強化され、対応の遅れは市場アクセスや資金調達のリスクに直結するようになりました。
消費者側でも、Z世代を中心に「環境・倫理に配慮した企業を選ぶ」という価値観が顕在化しています。さらに、優秀人材の獲得競争や、持続的なイノベーション創出の必要性といった内部要因も加わり、サステナビリティ経営はもはや企業の選択肢ではなく、存続と成長の前提条件となりつつあるのです。
CSR・ESG・SDGsとの関係性-混同しやすい概念の整理
サステナビリティ経営に関連する概念は、次のように整理できます。
- CSR(企業の社会的責任):企業市民としての基本的な責任。法令遵守や地域貢献など
- ESG(環境・社会・ガバナンス):投資家が企業を評価する非財務的な観点
- SDGs(持続可能な開発目標):国連が定めた2030年までの世界共通の目標
- サステナビリティ経営:上記すべてを包含し、事業戦略として統合する経営手法
これらの概念を正しく理解し、目的や対象に応じて連携・活用することで、ステークホルダーに対して一貫性のある効果的なコミュニケーションが可能になります。
従来型経営との決定的な5つの違い

サステナビリティ経営は、従来の経営とは発想そのものが違う、新しい考え方です。ここでは、従来型経営との5つの決定的な違いを解説します。
時間軸:四半期決算から長期価値創造へ
サステナビリティ経営では、従来の短期利益最大化から、10年・20年先を見据えた長期的価値創造へと時間軸を転換します。四半期決算の数字を追うだけでなく、将来世代のニーズを損なわない持続可能な成長を追求し、短期的なコストを長期的な投資として捉え直します。
例えば、再生可能エネルギーへの転換は初期投資が大きくても、長期的にはエネルギーコストの削減と炭素税リスクの回避につながります。この時間軸の転換により、研究開発投資、人材育成、ブランド構築など、短期的には費用となる活動が、長期的な競争力の源泉として再評価されます。
対象:株主第一主義から全ステークホルダーへ
株主利益の最大化だけでなく、従業員、顧客、取引先、地域社会、環境など、全てのステークホルダーの利益をバランスよく考慮する「ステークホルダー資本主義への転換」も求められます。
これは単なる理想論ではなく、各ステークホルダーとの良好な関係が企業の持続的成長に不可欠だという認識に基づくものです。従業員のウェルビーイング向上は生産性向上につながり、サプライヤーとの公正な関係は安定調達を実現し、地域社会への貢献は企業が安心して事業を継続するための土台となります。
指標:財務一辺倒から非財務指標の統合へ
売上・利益といった財務指標だけでなく、CO₂排出量、従業員エンゲージメント、顧客満足度、社会的インパクトなど、非財務指標を経営の中核KPIに組み込みます。そして、それらを統合報告書などで開示し、企業の価値創造プロセスを一体的に示すことが、サステナビリティ経営の基本姿勢です。
さらに、非財務指標と財務成果の関係を示し、こうした投資が企業価値向上にどう貢献するかを示すことも必要です。これにより、サステナビリティの取り組みを「コスト」ではなく「戦略的投資」として社内外で正しく位置づけることができます。
リスク管理:顕在リスクから潜在リスクへの対応
気候変動による物理的リスク、規制強化による移行リスク、人権問題による企業イメージの低下リスク、サプライチェーン分断など、将来顕在化する可能性のあるリスクを先取りして管理します。「何もしないことが最大のリスク」という認識のもと、シナリオ分析やストレステストを実施し、不確実な未来にもしなやかに対応できる体制を構築します。
例えばTCFDフレームワークに基づく気候関連リスクの開示は、この新たなリスク管理アプローチの代表例であり、2℃シナリオや4℃シナリオなど複数の未来シナリオに対する戦略的対応力が問われています。
価値創造の転換:社会課題の解決を成長の源泉に
企業の利益と社会の利益を対立関係ではなく、相乗効果を生む関係として捉え直します。CSV(Creating Shared Value:共有価値の創造)の概念により、社会課題解決が新たなビジネス機会となります。
例えば、高齢化が進む社会に向けた製品やサービスの開発は、課題解決と新市場の創出を同時に実現します。また、新興国で生活基盤を支えるBOPビジネスは、貧困の改善と市場開拓を両立させます。
この価値創造モデルの転換により、社会貢献は「コスト」から「投資」へ、そして「競争優位の源泉」へと変わるのです。
担当者が直面する「4つの壁」の全体像

理屈はわかる、でも進まない──その背景には共通する4つの壁があります。まずは、それぞれの壁の内容と、なぜ多くの企業が途中でつまずいてしまうのかを全体像として捉えましょう。
4つの壁の相関関係-負の連鎖を断ち切る
サステナビリティ推進では、4つの壁が次のような悪循環をつくります。
第1の壁:予算の壁(ROIを説明できず、予算が取れない)
第2の壁:社内浸透の壁(予算や後ろ盾がなく、全社の協力が得られない)
第3の壁:可視化の壁(活動の効果が見えず、評価・検証ができない)
第4の壁:リソースの壁(成果が見えないため、専任体制や人員が増やせない)
このループを断ち切るには、いずれかの壁を突破し、流れを「正のスパイラル」に変えることが大切です。第3の壁と第4の壁は、実行と成果の見える化を同時に進めることで、社内理解と改善の循環が生まれます。
企業規模・業界別の攻略難易度マップ
企業特性により、各壁の高さと攻略法は異なります。大企業では社内調整の複雑さから第2の壁(全社巻き込み)が最大の課題となり、中小企業ではリソース不足から第4の壁(リソースの確保)が深刻です。
製造業では環境データの測定は比較的容易ですが、サービス業では第3の壁(成果の可視化)に苦労します。金融業ではESG投資への対応が急務となり第1の壁(予算の確保)は低いものの、実業を持たないため実行面で課題があります。自社の特性を踏まえ、最も効率的な突破戦略を立てることが重要です。
第1の壁(予算の壁)を突破する:経営層の理解と予算獲得

まずは、「投資と対効果が見えにくく、予算が取れない」という第1の壁の突破方法です。
「それは具体的にいくらの利益を生むのか?」という経営層からの問いは、サステナビリティ担当者が最初に直面する壁です。
ここでは、サステナビリティを「戦略的投資」として位置づけ、経営層の理解と予算を獲得する方法を紹介します。
企業価値を直接向上させる4つの経営メリット
サステナビリティ経営は、単なる社会貢献ではなく企業価値を高める戦略です。主に以下の4つの観点で効果を発揮します。
- 資金調達面:ESG評価が高い企業には、融資条件の優遇や投資家からの支持が集まりやすくなります。
- 人材面:企業の姿勢を重視する若手や専門人材から選ばれやすく、離職の抑制にもつながります。
- ブランド・収益面:環境・社会に配慮した企業は価格競争に陥りにくく、ブランド価値や選ばれる理由を持てます。
- 新規事業機会:脱炭素・循環型社会などの潮流が、新たな市場やパートナーシップを生み出します。
こうした効果を財務視点と結びつけて語ることで、経営層の理解と投資判断を得やすくなります。
無形価値・リスクを財務的に見える化
従業員エンゲージメントの向上や離職の抑制といった無形価値は、そのままでは財務指標に現れません。
しかし、採用・育成にかかるコストの削減効果として金額換算することで、投資対効果として経営層に伝えやすくなります。たとえば、離職が減ることで新規採用や教育の負担が軽くなり、生産性の維持にもつながります。また、サプライチェーンからの排除や主要取引先との取引停止といったサステナビリティ対応不足によるリスクも、失われる売上や機会損失として評価できます。
こうした可視化は、サステナビリティ投資を「コスト」ではなく、企業を守るリスクマネジメント、さらには将来の収益を支える戦略的投資として位置づける助けになります。
第2の壁(社内浸透の壁)を突破する:全社巻き込みと実行

続いて、「他部署の協力が得られない」という、第2の壁の攻略法についてです。
サステナビリティ推進室だけの活動では限界があります。他部署を「自分ゴト化」させ、全社的なムーブメントを創出する具体的手法を解説します。
現状分析とマテリアリティ特定-重要課題の見極め
全社を巻き込む第一歩は、自社にとって本当に重要な課題を特定することです。バリューチェーン全体での環境・社会への影響を分析し、ステークホルダーとの対話を通じて期待と要請を把握します。
例えばGRIスタンダードのマテリアリティ・マトリックスを用いて、「ステークホルダーにとっての重要度」と「事業への影響度」の2軸で課題をマッピングしてみましょう。そうすれば、限られたリソースを最も効果的な領域に集中できます。
重要なのは、このプロセス自体に各部門を巻き込むことで、課題を「自分ゴト化」してもらうことです。
部門別メリットと紐づけた実行計画
各部門のKPIとサステナビリティ活動を連動させることで、全社的な推進力を生み出します。
営業部門には「サステナビリティを差別化要素とした提案力の強化」、製造部門には「省エネ・省資源によるコスト削減と品質向上」、人事部門には「採用ブランド力強化と従業員エンゲージメント向上」など、各部門の目標達成に貢献する形でサステナビリティ施策を設計するとよいでしょう。
小さな成功体験と体験型研修でモメンタムを作る
全社的なムーブメントを創出するには、早期の成功体験が不可欠です。3ヶ月で成果が出る小規模プロジェクト(省エネ、ペーパーレス等)から始め、その成果を社内報やイントラネットで大々的に共有します。
こうした社内のモメンタムづくりには、体験型の研修やイベントの活用も効果的です。JTBでは、社員が脱炭素の本質を「体験を通じて理解」できるプログラムとして、「脱炭素まちづくりカレッジ」を提供しています。
講義だけでなく、ゲームを通じて自ら体験することで、サステナビリティを「自分ゴト化」する設計となっており、社内の行動変容を促す実践的な手法として注目されています。
第3の壁(可視化の壁)を突破する:成果の可視化と効果測定

3つ目は、「活動の効果が見えにくく評価されない」という第3の壁への対処法です。
「活動はしているが、成果が見えない」という悩みも、多くのサステナビリティ担当者に共通しています。ここでは、活動の効果を財務価値として可視化し、説得力のあるエビデンスとして提示する方法を紹介します。
サステナビリティ活動を「財務価値」に変える方法
サステナビリティの取り組みも、工夫次第で財務的な価値として示すことができます。たとえば、CO₂削減は「エネルギー使用量の削減=電気・ガス代の削減効果」として計算できます。また、将来の炭素税や排出権コストの回避につながる点も、投資判断の材料になります。
廃棄物や水の削減も同じで、「処理費用・上下水道料金を減らせる=コスト削減効果」として評価できます。さらに、環境配慮によって商品・サービスの付加価値が高まり、価格面で評価されるケースもあります。
こうした数値は専門家しか扱えないものではなく、エクセルなどを使って計算できる形に落とし込むことが可能です。
KPI設計と進捗管理 ― 目標と測定をセットで考える
サステナビリティは「やっているかどうか」ではなく、「どれだけ成果につながっているか」が問われます。そのためには、目標(KPI)と測定方法をセットで設計することが大切です。
CO₂削減や人材・社会への取り組みなどの指標は、国際的な基準(SBT・GRIなど)を参考にすると、投資家や取引先にも伝わりやすくなります。また、進捗状況をダッシュボードなどで見える化しておくことで、現場での改善や部門間の連携がスムーズになり、形だけの取り組みではなく「動く仕組み」へと変わります。
国際基準での開示と、第三者の目を活かす
サステナビリティ活動を社外に伝えるときは、独自の表現ではなく、国際的に認められた枠組みで整理することが重要です。TCFDによる気候関連情報の開示や、GRIスタンダードに沿ったサステナビリティ報告書は、その代表的な方法です。
さらに、ISO認証、SBT認定など第三者による認証を活用すれば、「自社の評価ではなく、客観的に認められた取り組み」として信頼性が高まります。つまり、透明性と信頼性をどう担保するかが、投資家・顧客・取引先との関係に直結します。
第4の壁(リソースの壁)を突破する:推進体制とリソースの確保
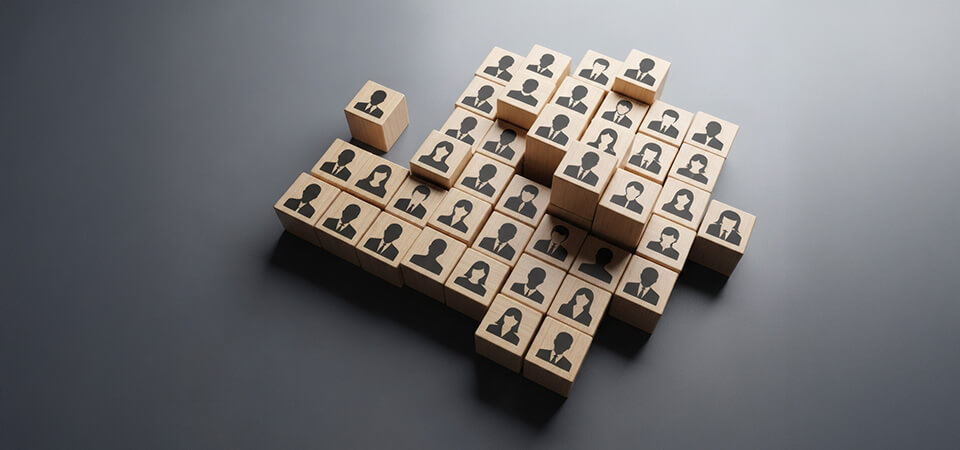
最後は、「専門人材や体制が整わない」という第4の壁の解決策です。限られた社内リソースで最大の成果を出すための組織設計と、外部リソースの戦略的活用方法を解説します。
推進体制の類型と最適な組織設計
推進体制には、大きく4つのパターンがあります。
| 体制 | 特徴 |
|---|---|
| CEO直轄型 | トップの意思決定が早く、大企業・変革期向け |
| 委員会型 | 各部署横断でバランスを取りやすい |
| 専門部署型 | 専任チームで実行力が高いが、人員確保が必要 |
| マトリクス型 | 既存の事業部と連携しながら推進でき、多くの日本企業で採用されやすい |
重要なのは「どの型が正解か」ではなく、企業規模や進捗段階にあわせて最適な型を選択し、移行していくことです。特にリソースが限られている場合は、いきなり専任部署を設置するのではなく、まずは既存部署の兼務で構成する「委員会型」から始め、活動が軌道に乗ってから専門部署型へ移行するのが現実的です。
外部パートナーは共創パートナーとして選ぶ
サステナビリティ経営では、気候変動、人権、サプライチェーン、ESG開示など専門性の高いテーマが多く、すべてを自社だけで担うのは現実的ではありません。そこで、外部の知見や技術を活用することが重要になります。代表的なパートナーと、その活用領域は次の通りです。
| パートナー | 主な役割 |
|---|---|
| サステナビリティコンサルティング | 戦略設計・ロードマップづくり |
| 認証・評価機関(SBT・ISO・CDPなど) | 科学的根拠に基づく目標設定や第三者評価の取得 |
| 共創型パートナー(地域・社会課題との接点を持つ組織・企業)NPO/NGO・産学連携 | 人権・地域共生・脱炭素など社会課題への実践的知見 |
| 実行支援パートナー社内浸透・行動変容支援(研修・M&E・イベント等) | 社員・ステークホルダーへの理解促進、共感醸成、行動変容支援等(研修の実施・イベントの脱炭素化支援等) |
ただし重要なのは、業務を丸ごと任せるのではなく、「社内で方針を持つ → 外部の専門性で補完する → 自社として判断し、開示する」という流れで共に進めることです。
CSR時代とは異なり、結果責任も説明責任も企業自身に残る領域だからこそ、社内の意思決定と外部知見を組み合わせた体制づくりが求められます。
サステナビリティを浸透させるには?

サステナビリティ経営を根づかせるには、理念や方針を伝えるだけでは不十分です。社員一人ひとりが自分ゴトとして捉え、日々の業務に結びつけられるようにすることが重要です。そこで効果を発揮するのが、M&E(Meeting & Event)です。
理念を「体験」に変え、社内の共感を生む
人は理屈を聞くだけでは動きませんが、体験を通じて納得すれば自発的に動けるようになります。研修や周年イベント、地域共創フォーラムなどの「体験の場」を通じて、サステナビリティの意義を「感じて理解する」ことは、組織全体の意識を一方向に揃えるうえで有効です。
M&Eという非日常の場を活用し、社員の意識を「他人事」から「自分ゴト」へと変えることこそが、実装スピードを加速させる鍵となります。
イベントの脱炭素化で、本気度を可視化する
さらに、イベントそのものをサステナブルに設計することも、企業姿勢を示す有効な手段です。例えばJTBでは、イベント開催に伴うCO₂排出量をカーボン・オフセットする「CO₂ゼロMICE®」を提供しています。
イベント全体の環境負荷を見える化し、実質ゼロにすることで、企業の脱炭素への取り組みを社内外に発信することが可能です。こうした「体験を通じた浸透」と「イベント自体の環境配慮」を両立させることで、サステナビリティ経営の実装はより深く、持続的なものになります。
サステナビリティ経営の実践事例

サステナビリティ経営は理念だけではなく、現場への浸透と継続的な仕組み化が重要です。ここでは、JTBのサポートも活用しながら、環境・社会・経済の視点を経営に取り入れている企業の事例を紹介します。
01 フエニックス・コンタクト株式会社 様100周年を機にサステナビリティ経営を加速した事例
02 三重県鳥羽市 × 浜倉的商店製作所 様地域と企業が共創するサステナブルなまちづくり
03 株式会社秋田スズキ 様脱炭素の見える化を実現した「地球にやさしい招待旅行」
まとめ

サステナビリティ経営は社会貢献ではなく、企業の競争力・信頼・人材獲得を支える「経営戦略」です。ただし現場では、ROIの証明や社内浸透、成果の可視化、リソース不足といった壁に直面し、理念倒れになりやすいのも現実です。
大切なのは完璧な仕組みづくりよりも、自社にとって重要なテーマを見極め、小さな実践と可視化を積み重ねることです。成功事例が社内の共感と次の挑戦を生み、取り組みは「続く仕組み」へと変わっていきます。
JTBでは、ビジョン設計から人材育成、社内浸透、地域共創プロジェクトまで、サステナビリティ経営の実装を伴走型で支援しています。自社に合った進め方を検討される際は、ぜひご相談ください。


